| ルート・シー インタビュアー |
碾茶(てんちゃ)は、抹茶の元になる茶葉とのことですが、
昔から飲まれていたお茶なのですか?
|
| 安井 |
いえ、碾茶を飲む機会はほとんど限られています。
千利休の時代から、碾茶を碾茶として飲む作法はなかったんですね。
茶道でも碾茶は認められていません。
|
| ルート・シー インタビュアー |
では、どのような機会に飲まれているのですか?
|
| 安井 |
抹茶の品質を審査するときですね。
というのも、碾茶から抹茶の状態にするには、石臼で挽かなあかんのですね。
電動でも、1時間で40グラムとか80グラムとかですよね、
ここで挽かれても。
|
| 高木 |
ええ。
|
| 安井 |
一服大体1.8グラムですけど、もし手挽きでやろうとしたら、
10分以上かけてもなかなか挽けません。
そういう理由で、抹茶の状態にして審査はでけへんのですよ。
碾茶の状態で、外観とか、お湯を通してからの色とか、香気、滋味。
あと、お湯を通したあとの葉っぱの「から色」いうんですけど、
そういう審査項目で茶葉の評価をするんですよね。
|
| ルート・シー インタビュアー |
抹茶だと時間がかかるので、碾茶で評価をするということなんですね。
その時は、碾茶を飲まれていた、と。
|
| 高木 |
そうです。碾茶を飲んで評価しています。
|
| 安井 |
玉露、煎茶というのは、生の芽を摘んできて、
それを揉み込みながら乾燥させるんですね。
揉むのは何故かと言うと、茶葉の細胞壁をこわして、
お湯に通した時に成分が抽出されやすいようにしているわけなんです。
ところが碾茶は、石臼で挽いて、シャカシャカ立てて、
最終形になる前提で製造されてますので、揉む必要が無いんですね。
蒸してから乾かすだけなんです。
揉んでないので、細胞壁もそれほど傷んでいません。
|
| ルート・シー インタビュアー |
玉露や煎茶に比べて成分が出にくいということでしょうか。
|
| 安井 |
そう、出にくいんです。
玉露や煎茶は揉み込んでいるので、雑味とかも含めて、
良くも悪くも茶の成分が出やすいんですね。
一方、碾茶は揉み込んでいないので、雑味が出ません。
ピュアな滋味しか出ないんですよ。
|
| ルート・シー インタビュアー |
試作品をいただいた時、確かにそんな感じがしましたね。
お茶そのものの味という感じでした。
|
| 安井 |
茶道でも認められてなくて、流通もしてなかったので、
碾茶のピュアな滋味は、お茶屋しか知らなかったんですよ。
|
| ルート・シー インタビュアー |
お茶屋さんしか知らなかった美味しさ…
今回はその美味しさを届けられる、ということですね。
|
| 安井 |
抽出されにくいというのはあるんですけど、
そこさえクリアすれば、あの神秘的な味を楽しむことができる、と。
|
| ルート・シー インタビュアー |
確かに飲んでみても、雑味はないですよね。
会社で、普段お茶をあまり飲まないような人でも、全然違うと言ってます。
この味なら、私たちなりに表現したかった「驚き」といったようなことも、
今回、碾茶をティーバッグにするというアイディアをいただけたおかげで、
お客さんにもお届けできるんじゃないかなと思っています。
|
| 安井 |
もう一つ、贅沢さという面で、お話を。
抹茶というのは、石臼で挽いて、シャカシャカ立てて飲みますから、
100%摂取できますでしょ?
1.8グラムで一服分できるわけなんですけど、
そういう前提で、原価構成が考えられているわけなんです。
それに対して、碾茶で抽出すると、
しっかり抽出しても水溶性の成分が30%しか出なくて、
ビタミンEとかベータカロチンとか、油溶性の成分は、
100%抽出されないんですよ。
しかも、一服分は4グラムくらい要るんです。
そう考えると、抹茶として飲むよりも非常に贅沢なんですよね。
碾茶というのは、そういう贅沢な楽しみ方をしてると。
|
| ルート・シー インタビュアー |
そもそも飲む機会のほとんどない碾茶っていうのは、
やはり流通してないものなんですか。
|
| 高木 |
食べるお茶としては、一部流通してますね。
|
| ルート・シー インタビュアー |
飲むのではなく、葉っぱ自体を食べる、ということですか。
|
| 高木 |
そう。茶葉が柔らかいんです。
|
| 安井 |
でも、消費者目線で見た場合、ほとんど見かけませんね。
|
| 高木 |
そうですね、高価ですから。
一部の料亭で使ってもらってるとか、ですね。
高価になる理由は、作り方を考えると当たり前なのかなと思います。
碾茶と、一般の露地ものと呼ばれる煎茶なんかとでは、
肥培管理に大きな違いがあります。
それと、覆いをするということでの良さ。
旨味を蓄えるとかテアニンが豊富になるとか、
そういった部分での良さがありますので。
どんな作物でもそうだと思うんですが、手間をかければ旨くなります。
お茶もいっしょです。
それで、その味があるから評価もされて、高価なものになると。
だから、なんで市場に出回ってないかというと、
そんな高いものは、誰も飲まないからですね。
あと、手間が…かかるんですね。
例えば、ティーバッグに入れようとすると、
ある程度の形まで作り込まないといけません。
普段は、石臼にかかる分の大きさに揃えていくわけなんですが、
今回は、そこからティーバッグ用に再度選別して、
仕立て直したんです。
久しぶりに「篩(とおし)」を使って。
|
| 安井 |
手作業で。(笑)
|
| ルート・シー インタビュアー |
「篩(とおし)」というのは道具のお名前ですか、どういうものですか?
|
| 高木 |
「ふるい」がありましてね。
機械っていうのは、均一にものを作っていくんですが、
均一さ自体は見てないんです。
手作業でふるいをすると、その大きさを目で見ながら調整できるんです。
速く回したり遅く回したり。
そういったことができるので、今回は手作業でやりました。
|
| ルート・シー インタビュアー |
はあー、すごい。
|
| 高木 |
手作業のものは、やっぱりうまいんです。
「手仕込み」とか、よくありますよね。
あんなのも、機械で全部作るのと、手でやるのとでは、全く違うわけです。
その肌触りとか。
お茶も、仕立てる時に刻んだり、潰してたりしていくわけです。
「ふるい」っていうのは、まあ網ですよね。
その網を縦に振るとお茶は立って、下にスポっと落ちますし、
回してやると長さが揃うんです。
そういうことを、昔は全部手作業でやってたんですが、
大量にものを作るために機械化したんですね。
機械は、一定の作業をすることはできますけど、
そのお茶、その素材に合わせた仕立てはできません。
全部一律ですね。
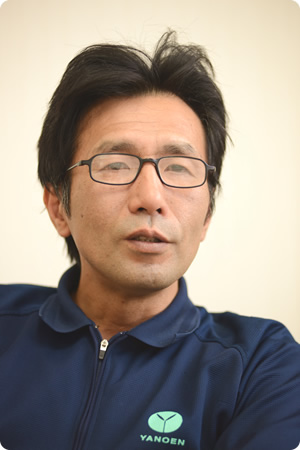
|
| ルート・シー インタビュアー |
確かに一旦セットしたら、そのままのイメージですよね。
|
| 高木 |
ある程度は設定できますけどね。
でも、やっぱり、お茶を「磨く」っていうんですけど、
磨こうとすれば、手作業の方が良いです。
見ながら、形を整えながら、それで最後は刻んでいくんですけど、
これも手作業でやります。
お茶をゴシゴシと網の上でこすって、潰していきながら。
ティーバッグに合う形に仕立てたんです。
|
| 安井 |
普段使わへん体使こて、ええ刺激になりましたね。
|
| 全員 |
(笑)
|
| 安井 |
碾茶は特にしっかり出さな旨味が出し切られへんというお話で。
僕がサラリーマンの時にですね、取引先の役員さんに
「僕の地元で採れた玉露と煎茶なんです」と言って、
上等な手摘みのものをさし上げたんですよ。
そうしたら、次にお会いした時、
「安井さん、あれのおかげで、週末に家内との会話が増えちゃいましてね。
夫婦円満のツールですね、これ」
とおっしゃっていただきました。
今回の碾茶も、待ち時間はなかなか大変かもしれませんけど、
人と人を繋げる接着剤にもなると(笑)。
|
| ルート・シー インタビュアー |
いいですよね、待ち時間も。
今回、お客さまにお持ちするために作っているわけですけど、
待っている間に、そういう会話を楽しんだりして欲しいと思っています。
|
| 高木 |
正直、碾茶がうまいと感じて飲んでもらえるというのを、
今まで提案してなかった。
碾茶は、元々抹茶の原料にするものだという認識が僕らには強くて、
流通させようという考えはなかったです。
|
| ルート・シー インタビュアー |
すみません、素人が無理なお願いをして…
実際それを作られて、飲まれて、どういう感覚でした?
|
| 高木 |
まあ、試験する段階では飲んではいたんですけど、
そういうものを通常の飲用にするという感覚はなかったですからね。
お茶屋にしてみれば、もう、最初からこれは抹茶の原料だ、と。
その固定観念が崩れたというか、先ほどもありましたが
いい刺激になりました。
それにしても、昔から消費者にも碾茶が飲まれなかったのは、
なんでですかね?
|
| 安井 |
おそらく昔は、栄養源としてお茶が飲まれてたんですよ。
例えば雪深い所だったら、冬場ビタミン摂取しにくいから、
お茶をしっかり飲んで摂取するとか。
だから、石臼で挽くための碾茶を
わざわざ急須で入れるようなことはしなかったんですよ。
さっきの原価構成の話じゃないですけど、
そんなもったいない、贅沢なこと、アホなことだったんでしょうね。
|
| ルート・シー インタビュアー |
なるほど。
|
| 安井 |
ところが今、こんだけビタミン摂取の方法がある中で、
どうやったら、お茶に興味を持ってもらえるか。
今の時代では、いろんな説明とか背景がくっついてこないと
お客さんの触手が伸びないんですよね。
ワインとかでもそうじゃないですか?
だから逆に、昔は罰当たりとか言われていたことが、
今は面白がられるようになるんじゃないかな、と。
|
| 高木 |
今の時代みたいに、お茶に対して何を求めるのか。
飲み物も、ただ旨いというだけでなく、
その飲み物が作り出す空間とかシーンなんかも含めて、
そういうものを楽しむ癒しのツールとして受け入れられるんだったら、
費用がかかってもやる価値がありますよね。
だから、旨味だけが引き出される碾茶っていうのは、
これから流通するのかもしれないですね。
商品として出していくのに、面白みがあると思います。
|
| 安井 |
その不便さが嬉しさに変わるんですよね。
時間がかかるとか、沈めなきゃいけないとかね。
従来の考え方では、売れにくいものなんですが、
これからは、そういうのが面白いんですよね。
|
| ルート・シー インタビュアー |
そうですね。
|
| 高木 |
あと、流通しなかった理由としては、「半製品」だったということですね。
碾茶はあくまで、抹茶を作る工程の途中で作られる「半製品」だったと。
だから世の中に出してなかったんです。
そういうのって、見直してみると、結構あるかもしれないですね。
|
| ルート・シー インタビュアー |
忘れられてた価値かもしれないですけど、
逆に言うとそれは新発見とも言えますし、
それが付加価値になってきますよね。
|
| 高木 |
そう言えば、湯葉って半製品ですよね?
|
| 安井 |
そうですね。
|
| 高木 |
でも、高級品ですね。
|
| 全員 |
(笑)
|
| 高木 |
碾茶も、やがてそうなるかな?(笑)
|